メンバー
農学研究科

プログラム長
野地 智法
農学研究科 教授
機能形態学・粘膜免疫学

農学研究科長
北澤 春樹
農学研究科 教授
畜産食品・飼料免疫学
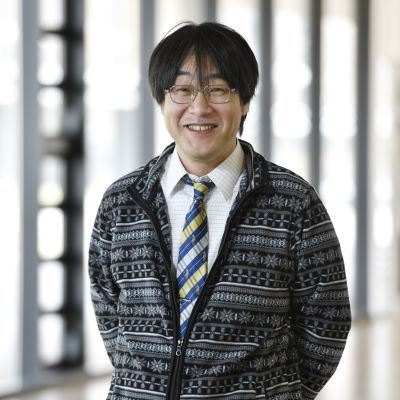
佐藤 幹
農学研究科 教授
動物栄養生化学
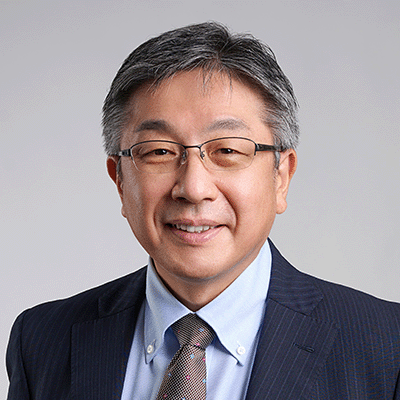
白川 仁
農学研究科 教授
栄養化学・分子栄養学

Cheryl Lynn Ames
農学研究科 教授
国際海洋科学

戸田 雅子
農学研究科 教授
食品免疫学・分子アレルギー学

原田 昌彦
農学研究科 教授
分子生物学・細胞生物学・放射光X線利用

冬木 勝仁
農学研究科 教授
食料政策・食品流通

片山 知史
農学研究科 教授
水産資源生態学
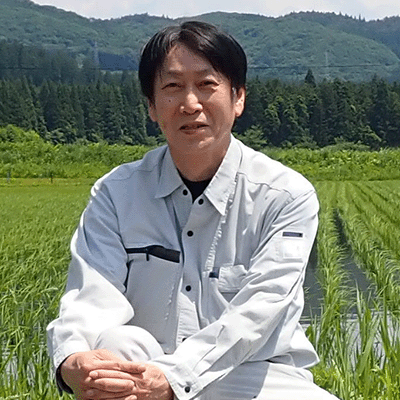
西田 瑞彦
農学研究科 教授
生産土壌肥料学

本間 香貴
農学研究科 教授
作物学

藤井 健太郎
農学研究科 客員教授
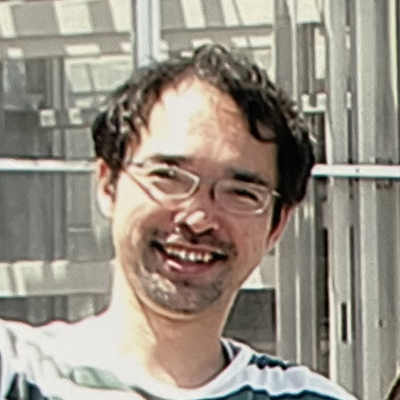
山本 雅也
農学研究科 准教授
植物分子生物学
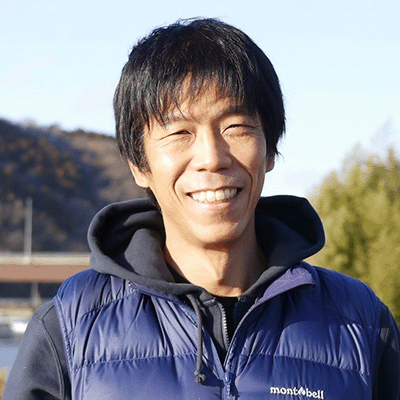
藤井 豊展
農学研究科 准教授
海洋生態学・環境管理

堀籠 智洋
農学研究科 准教授
分子生物学

大崎 雄介
農学研究科 准教授
栄養生理学

西山 啓太
農学研究科 准教授
微生物学・畜産食品

井元 智子
農学研究科 准教授
環境経済学

水木 麻人
農学研究科 准教授
農業経済学・農業経営学
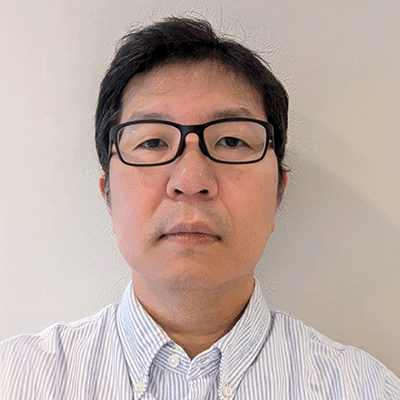
日髙 將文
農学研究科 助教
酵素学・分析科学
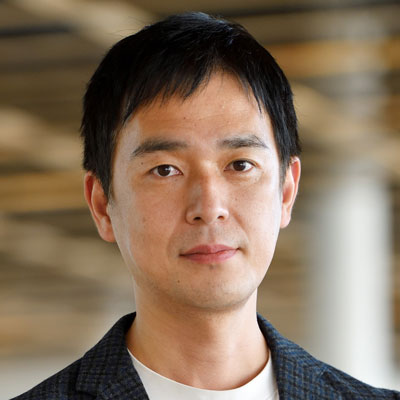
長澤 一衛
農学研究科 准教授
二枚貝の生殖生理学
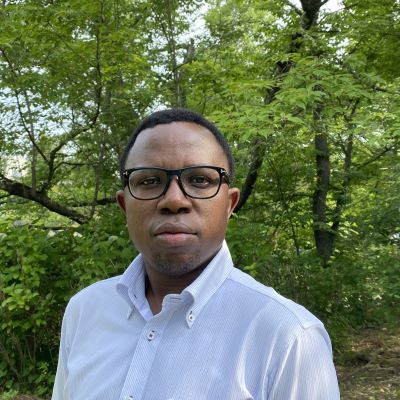
Magezi Eustadius Francis
農学研究科 助教
農業経済学

KEENI MINAKSHI
農学研究科 助教
開発政策学・ジェンダー研究・家計調査
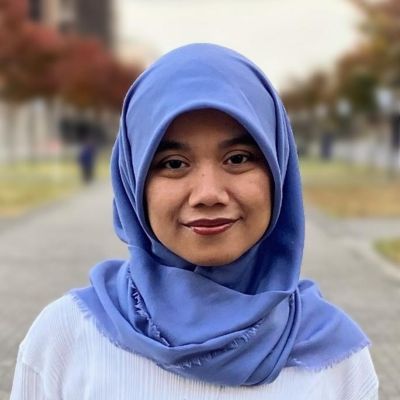
Afifah Zahra Agista
農学研究科 助教
食科学・栄養学
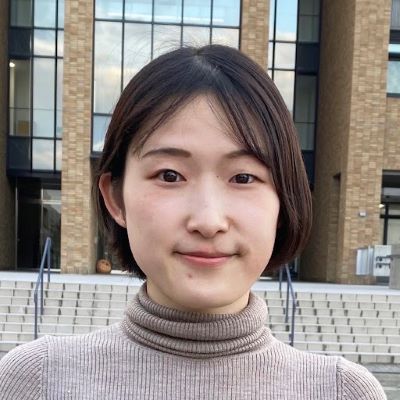
小山 紗江佳
農学研究科 助教
粘膜免疫学
医学系研究科

医学系研究科長
石井 直人
医学系研究科 教授
免疫学・小児科学
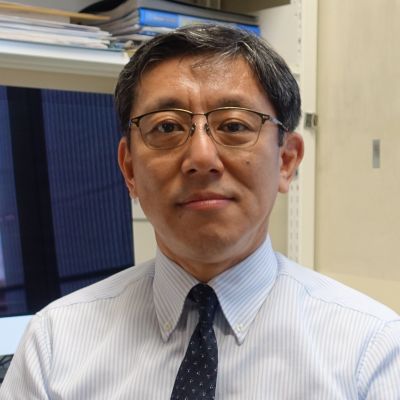
今谷 晃
医学系研究科 教授
消化器内科学
歯学研究科

歯学研究科長
小坂 健
歯学研究科 教授
公衆衛生・社会医学
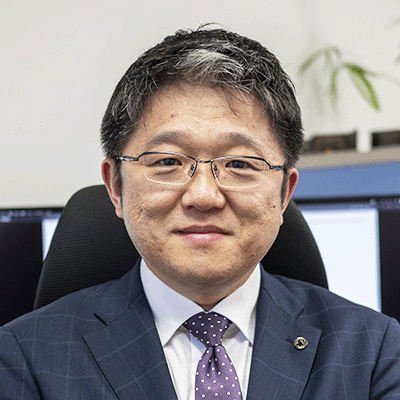
洪 光
歯学研究科 教授
生体材料学・老年歯科医学

菅原 俊二
歯学研究科 教授
口腔微生物・免疫学

高橋 信博
歯学研究科 教授
マイクロバイオーム生化学

若森 実
歯学研究科 教授
神経科学・神経薬理・歯科薬理学

服部 佳功
歯学研究科 教授
老年歯学・歯科補綴学
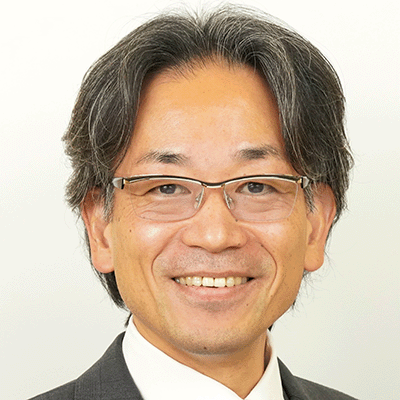
江草 宏
歯学研究科 教授
再生歯学・歯科補綴学
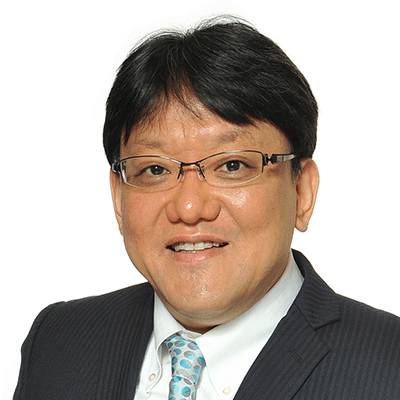
金髙 弘恭
歯学研究科 教授
歯学・医工学・歯科矯正学

飯久保 正弘
歯学研究科 教授
顎口腔領域の画像診断・周術期患者の口腔管理

齋藤 幹
歯学研究科 教授
小児発達歯科学分野

鷲尾 純平
歯学研究科 准教授
歯学・口腔生化学
薬学研究科

倉田 祥一朗
薬学研究科 教授
ショウジョウバエを用いた分子遺伝学
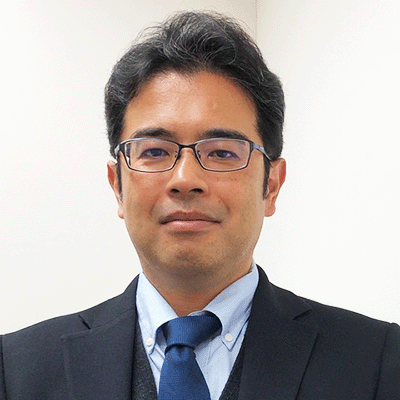
斎藤 芳郎
薬学研究科 教授
環境衛生・微量元素

外山 喬士
薬学研究科 講師
毒性学・ケミカルバイオロジー
文学研究科

坂井 信之
文学研究科 教授
食行動の心理学

川口 幸大
文学研究科 教授
文化人類学
国際放射光イノベーション・スマート研究

国際放射光イノベーション・スマート研究センター長
千葉 大地
国際放射光イノベーション・スマート研究センター 教授
デバイス工学

吉田 純也
国際放射光イノベーション・スマート研究センター 准教授
素粒子原子核物理学
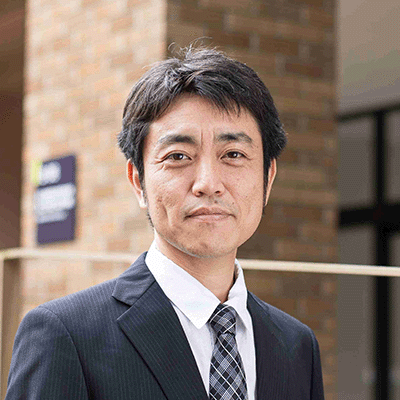
星野 大樹
国際放射光イノベーション・スマート研究センター 准教授
ソフトマター物性

湯川 龍
国際放射光イノベーション・スマート研究センター 准教授
低次元電子の制御

Zhong Yin
国際放射光イノベーション・スマート研究センター 准教授
複雑な化学システムにおける
超高速X線分光法

高山 裕貴
国際放射光イノベーション・スマート研究センター 准教授
放射光X線イメージング

